みなさんこんにちは!
本日は、これまでの管理栄養士国家試験に関するお話の中で何度か話題に挙げてきた、「管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)」について、しっかりとお話ししていきたいと思います!
このガイドライン、量が多くてしっかり読むのは面倒くさいと感じる方も多いと思います。
ですが、試験範囲を知るために、ざっくりとでも良いのでぜひ1度目を通してみてください!
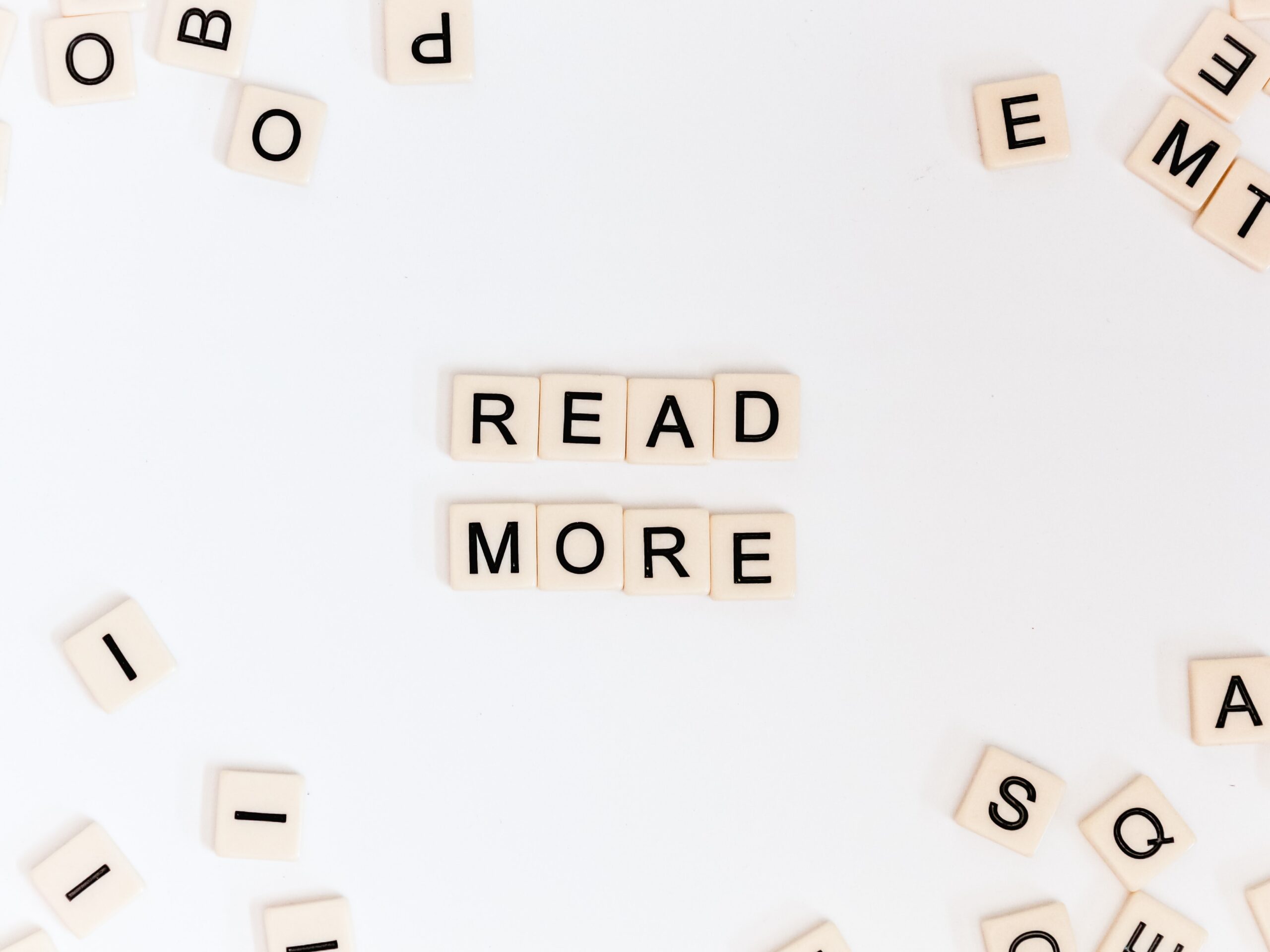
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)とは??
ガイドラインは以下のように定義されています。
定義
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)は、管理栄養士国家試験の「妥当な範囲」と「適切なレベル」とを項目によって整理したものであり、試験委員が 出題に際して準拠する基準である。
したがって、管理栄養士国家試験出題基準は、管理栄養士養成課程の教育で 扱われる内容の全てを網羅するものではなく、また、これらの教育のあり方及び 内容を拘束するものではない。
(01報告書前文 (mhlw.go.jp)より抜粋)
何やら難しく書かれていますが、要はこのガイドラインを参考に問題を出題するということです。
逆説的に、このガイドラインになければ国試に出題されることはまずないということでしょう。
もちろん、ガイドラインはほとんどの専門科目を網羅していますので出題されない範囲を探すよりもまんべんなく勉強をする方が良いと思われます。
ガイドラインの改定について
ガイドラインは概ね4年に1度改定されています。
前回の改定は2019年(第34回国家試験)で、その際にはそれぞれの問題数に大幅な変更が生じています。
このガイドラインの変更によって、今まで出題されていなかった内容が出題されるようになるかもしれません。
今年はガイドライン改定の年ではありません。
ですが、来年以降に国試を受験する場合(特に2023年)は、ガイドラインの変更があるかもしれないと注意する必要があります。

本日のまとめ
本日は、管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)についてお話ししました。
残念ながら、ガイドラインを読んだからといって国試の問題が解けるようになるということはありません。
ですが、自分が受験する試験について、ある程度の情報を入手することは確実にメリットがあります。
そう思われる方は、まず苦手な科目のガイドラインに目を通していきましょう。
それでは、また次回の投稿でお会いしましょう!


コメント